――この町の夏は、耳鳴りみたいに続く。
一学期の終わり、蝉がいっせいに鳴き出した頃、僕らは四人になった。
水守秋良(みずもり・あきら)、早瀬真帆(はやせ・まほ)、風間透(かざま・とおる)、そして――相河灯子(あいかわ・とうこ)。
灯子は夏休み中に引っ越してきた。自治会の回覧板を届けにいった真帆が、玄関先で見つけたのだという。
「二学期から転校してくるって。今は荷ほどき中、だってさ」
そう言った真帆の顔は、梱包材を破るみたいにわずかにほころんだ。
知らない子が地図に加わる、それだけで夏休みは少しだけ広がる気がした。
一 ご近所づきあいの裂け目
灯子の家は、町のはずれ――棚田の見下ろせる小高い丘にあった。風が曲がるところで、古い電柱がひとつだけ斜めを向いている。
彼女の母親は、涼しげな麦茶を僕たちに分けながら「何にもないところだけど、いい町ね」と言った。
「何にも、ない?」
真帆が眉を上げる。
「あるよ。戻らずの棚田、風穴、八月三十一日の逆さ祭り……」
「それ、観光パンフの話?」と僕が言うと、透が小声で続けた。
「パンフに載らないほうが多い。夜の田んぼで灯りを持った人に名前を呼ばれても、絶対に返事をしちゃいけない、ってやつとか」
灯子は、麦茶の氷をストローで追いかけながら、少し遠い目をした。
「……名前を呼ばれて、返事を、しない。約束、ね」
彼女の声は、どこかで何度も練習された合図みたいに正確だった。
その日の帰り際、僕らは玄関先の回覧板に貼られた古い紙きれに気づいた。
『夏越(なごし)之輪ノ裏通リ 安全ノ心得』
墨は褪せ、虫に食われている。けれど手書きの地図は鮮明だった。
鎮守の小社に置かれる茅の輪をくぐったあと、輪の“裏”に回り、影の段を三つ降り、風の骨の坂を上る――。
「裏通り?」
真帆が笑った。「ねえ、行こうよ。どうせ宿題は八月の終わりにやるんだから」
僕らは四人で、翌朝の集合を決めた。
二 茅の輪の“裏”
鎮守の小社は、昼寝する猫のように石段の上で丸まっていた。
境内には、茅の輪が夏の輪郭を描いている。輪をくぐるだけなら祭りの日の定番だ。だが、裏に回るなんて、聞いたことがなかった。
輪の影は、午前の光の上で濃かった。影の内側には、たしかに段が見えた。
土でも石でもない、黒い紙のような段。三段、降りるたびに蝉の声が遠ざかる。
「耳、詰まったみたい」
真帆が耳たぶを引っ張る。
透は、リュックに忍ばせた図鑑を握りしめていた。灯子は輪の縁をそっと撫で、ふっと指を離す。
裏側の空気は涼しく、匂いがなかった。
鳥居の影が、鳥居のない場所に落ちている。そこに“坂”が始まっていた。薄い、風の通り道だけでできた坂。
踏み出すと、足裏がわずかに浮く。
「ここが、風の骨……?」
透が言った。
坂は見えるのに、どこにも触れていない。風が見える骨格を持っているのだとしたら、それはたぶん、こういう形をしている。
坂を上る。
上るほど、僕らの影が薄くなる。反対に、手の中の小さなもの――真帆の髪留め、透の虫取り網、僕の母に借りた方位磁針、灯子の白いリボン――は、濃さを増す。
見えないものが見え、見えるものがほどけていく。
坂の頂には、田んぼが広がっていた。だが、水は空に張られ、稲は逆さまに揺れている。
空の水面を風が撫でると、金の波が裏返る。
「――裏の夏だ」
誰かが言った。たぶん僕だ。
三 稲の天と蛙の教会
裏の棚田を進むと、蛙の群れが列をなしていた。背中に小さな石の十字を背負い、礼拝の歌をうたっている。
歌は、人の言葉の手前でほどける。
「夜になっても、そこで眠らないように」
「名を三度、拾い上げないように」
「ねえ、拾い上げないって何?」
真帆がたずねると、蛙がいっせいに口を閉じた。石の十字に苔が生えはじめる。
「拾う、っていうのは」
灯子が、彼らの列に並ぶように膝をつき、石の十字の一つをそっと撫でた。
「呼ばれたとおりに、返事をすること」
風が通り、稲が逆さに鳴った。音は、学校のチャイムに似ていたが、始業でも終業でもない。
――別れの合図だった。
四 紙の海のほうへ
地図は続いていた。手書きの細い線が、田と田のあいだを縫う。
やがて水音がし、僕らは「紙の海」に出た。
本当に、紙でできた海だ。新聞紙の大波が折り畳まれてはほどけ、白い封筒が魚の尾びれのように揺れている。
ところどころ、宛名が読めた。どれも未投函のまま、宙を漂っている。
「これ、全部――」
透が封筒のひとつを掴もうとして、手を引っ込めた。紙の魚は噛む。
灯子は、波打ち際に落ちていた封書を拾い上げ、宛名を指でなぞった。そこには、見慣れた字で、こうあった。
『水守秋良様』
差出人のところは、空白のままだ。
僕が封を切ると、中からは紙ではないものが出てきた。
――錆びた鍵。
鍵穴のない鍵は、音だけがする。遠い、風鈴の、風がないときの音。
鍵を握ると、僕の影が少し濃くなった。
「戻り鍵だ」
灯子が言った。「帰るための鍵。でも、帰るたびに、ひとつ置いていかなきゃいけない」
「ひとつ、って……?」
「何か。夏に置いていけるもの」
真帆は髪留めを見つめ、透は図鑑の間からこぼれそうな押し葉を押さえた。
僕は、方位磁針をポケットに戻した。
灯子は、白いリボンをほどき、手首に結び直す。
紙の海の向こうに、坂がまた続いていた。風の骨は、町の地図の裏面を走る骨格で、場所と場所の間に秘密の距離を作っている。
僕らは骨の上を歩き、歩くたびに、何かを置いていった。蝉の声のひとかけら、汗の塩、麦茶の氷の音。
五 逆さ祭りの噂
裏の町には、人のいない祭りが準備されていた。金魚すくいの水は空に張られ、輪投げの輪は地面の影に投げられている。
射的の的は、夕焼けの端。
屋台の灯りはまだつかない。
「逆さ祭りは八月三十一日にやる」
透がつぶやいた。「僕たちの町でも同じ。だけど、裏のほうでは別のことが起きるらしい」
「たとえば?」
「たとえば、子どもが四人、約束を破る」
「約束?」
灯子は一瞬、視線を落とした。「名前を呼ばれても、返事をしない。拾い上げない。そういう約束」
「破ったら、どうなるの?」
答えの代わりに、風鈴が鳴った。鳴ったのに、風がない。
屋台の奥、空の水面の縁に、黒い人影が立っていた。形ははっきりせず、影だけが濃い。
――誰かが、僕の名前を呼んだ。
最初は、たしかに僕の名前に聞こえた。二度目は、僕が欲しいものの名前に聞こえた。三度目は、僕が一度も口にしたことのない、でもずっと知っていた言葉に聞こえた。
「返事、しちゃだめ」
灯子の指が、僕の袖をつまんだ。そうしなければ、僕は返事をしてしまっていた。
影は、ためらい、かすれて消えた。
「……もう、来てる」
灯子の声は、風の骨みたいに細く、でも強かった。
六 四人の午後
裏の夏は、時間が横に流れる。
朝と夕方が、重なって通り過ぎる。
だから、僕らは一日のうちに、いくつもの午後を持てた。
そのたびに、違う話をした。違う勇気を出し、違う嘘をつき、違う正直を拾った。
ある午後、透は蛙たちの教会で牧師をやった。
「今日の説教は、影の世話について。影は伸びたがるので、放っておくと夜に紛れて迷子になります。紐をつけて散歩させてください」
蛙たちは、苔の十字を揺らして笑った。
別の午後、真帆は空の田んぼで跳ね、逆さの稲穂の粒を捕まえようとした。
「ねえ、秋良。捕れたら、今日の夕飯にしよう。逆さのごはんって、美味しいと思う?」
「腹の中で、またひっくり返るかもな」
「それ、普通のごはんじゃん」
灯子は黙って、風の骨の節を確かめていた。
「ここ、折れてる。去年、誰かが強く踏みすぎたんだ」
「誰か?」
灯子は答えず、遠くを見た。
坂の向こうに、僕らの“学校”が見えた。昼の校舎は、鯨の骨格のように白かった。
「行こう」
灯子が言った。「学校の図書室に、鍵穴がある」
七 鍵穴のある図書室
図書室の扉は開いていた。司書の先生はいない。
書架は、ほんの少しずつ傾き、そこに並ぶ本の背が、息をしているみたいに膨らんだりしぼんだりしている。
机の上に、鍵穴があった。木目に溶け込む、ひとつの不自然。
僕が紙の海で拾った錆びた鍵は、そこにぴたりと合った。
鍵が回ると、僕の名前の一部が錠前に吸い込まれた。
――あ、
という音が、僕の喉から消えた。
秋良の「あ」が、少し薄くなった気がした。
「置いていったんだよ、秋良」
灯子が言った。
「帰るために、ひとつ」
錠前の向こうから、古い町の地図が引き出しのように現れた。
道は、僕らの知っている町とほとんど同じ――だけど、ところどころ橋が増えている。橋は、川に架かっていない。
影と影のあいだに、橋が架かっているのだ。
「これが、裏の橋」
透が指でなぞる。「渡るには、何かを置いていかなきゃいけない。橋は、対価でできてるから」
「何を置いた?」
僕がたずねると、透は笑って答えなかった。彼の笑いは、いつもより少し静かだった。
真帆は髪留めを指の腹で弾き、灯子はリボンの結び目を固くした。
「戻ろう」
灯子が言う。「逆さ祭りまでに、もう一度、表に」
鍵を抜くと、図書室の空気が少し重くなった。
僕らは風の骨を辿り、茅の輪の裏を三段、影の段を上がった。
蝉の声が一気に押し寄せてきて、世界に匂いが戻った。
八 表の夕立、裏の花火
表の町は、同じようで、少し違っていた。
灯子の家の前の斜めの電柱はまっすぐになり、代わりに別の電柱が斜めになっている。
僕の家の風鈴は、形がほんの少し楕円になっていた。音色は同じ、だから誰も気づかない。たぶん、僕たち以外は。
「ただいま」
僕が言うと、母は台所から「おかえり」を返した。その声は確かに母の声で、けれど、僕の名前の「あ」が一瞬だけ空気に引っかかった。
夕立が来た。
大粒の雨が、道路に白い文字を書いた。
『拾イ上ゲルナ』
『返事ヲスルナ』
『置イテ行ケ』
真帆が舌打ちした。「感じ悪っ……でも、ぜんぶ当たってる」
透は、電柱の影の長さを測ってから、小さく頷いた。
灯子は、雨の文字に靴の先で線を引き、指で消した。
「見なかったことに、しようか」
「できる?」
「できない。でも、やってみる」
夜、町の向こうで花火が上がった。
裏の夏のものだ。表からでも、あれは見える。
花火は、色ではなく、記憶を空に咲かせる。
小さな自転車に乗れた日、初めて手放しで笑った瞬間、井戸の底を覗いて青さに吸い込まれた午後――。
誰かの一瞬が、空でほどけてまた結ばれる。
「――きれい」
真帆が言い、透が「こわい」と続けた。
灯子は黙っていた。彼女の手首の白いリボンは、夜の中で光っていた。
九 八月三十一日の前日
夏休みの終わり。
宿題はまだ終わっていない。
裏の祭りの準備は、音もなく進み、表の神社には茅の輪が新しく据えられた。
回覧板には、また古い紙が貼られている。
『渡橋(ときょう)ノ儀 子供四名 夜半二時』
墨は新しい。誰かが今、書いたばかりだ。
「四名」
透が紙の上で指を止めた。
「僕ら、四人」
「儀式、なんていやな言い方」
真帆が紙を少し破りかけて、やめた。
「でも、これ、やれば――」
灯子が言いかけて、唇を噛んだ。
「やれば、町は守られる。台風が、来ない。田は倒れない。橋は落ちない。夏は、正しく終わる」
「代わりに?」
僕が問い、灯子は僕を見た。
「代わりに、何かが足りなくなる」
「誰の?」
「誰かの」
彼女の目は暗く澄んでいた。井戸の水を夜に見たときの黒さ。
僕はうなずいた。うなずくしかなかった。
十 渡橋
夜半二時。
僕らは神社に集まり、茅の輪の影を降りた。
風の骨の坂は、龍の背骨みたいに冷たく硬かった。
裏の祭りが、静かに始まっていた。
渡橋の場所は、紙の地図の上では空白のところにある。
表の町の地図に載らない“間”。
そこに、橋があった。橋は透明で、歩くと足音がしない。
川は流れていない。その代わり、名前が流れている。
誰かの名前、誰かの夏の呼び名、誰にも呼ばれなかったはずのあだ名。
名前は、それ自体で流れ、ぶつかり、泡立ち、消える。
「拾わないで」
灯子が言った。
「どれも、拾っちゃいけない」
橋の真ん中に、小さな台がある。そこに、置いていくものを置く。
僕は、方位磁針を置いた。
真帆は、髪留めを置いた。
透は、図鑑から一枚、押し葉を抜いて置いた。
灯子は、白いリボンを――結び目ごと、置いた。
風が止み、橋が鳴った。音は、花火のはじける前の静けさに似ている。
台の上の四つのものが、すっと沈んだ。
代わりに、僕らの足もとから影が伸び、橋に吸い込まれていく。
それは、橋の対価。
僕らは、夏の一部を渡した。
そのとき、向こう岸で、誰かが僕の名前を呼んだ。
一度目は、いつもの呼び方。
二度目は、僕が誰にも言わなかった願いを組み込んだ、呼び方。
三度目は――
灯子が僕の手を握りしめた。
「返事は、しない」
「でも――」
「しない」
真帆が、透が、僕の背中を押した。
僕らは返事をしないで、橋を渡り切った。
その瞬間、橋の両端で、何かが入れ替わる音がした。
空虚が満たされ、満ちたものが空虚になった。
十一 代償
翌朝、町は何事もなく晴れていた。
台風は進路を変え、棚田は倒れなくて済んだ。
電柱は、一本、斜めのままだった。
学校のチャイムは、始業の音を鳴らした。
八月三十一日は、終わった。
僕たちは四人で登校した。
通学路の柳は、まだ青かった。
なのに、校門のところで、見知らぬ四人組が笑いながら通り過ぎた。
――僕ら、に、似ていた。
彼らは、僕らよりも少しだけ鮮やかで、体温が高そうだった。
笑い声が、夏の終わりに似合っていた。
教室に入ると、担任が言った。
「相河灯子さんは、今日からこのクラスの仲間です」
拍手が起こる。
僕らは顔を見合わせる。
だって灯子は、もう――
灯子は、前を向いていた。
白いリボンは、どこにもなかった。
代わりに、彼女の髪の内側に、一本だけ白い糸が縫い込まれているのが見えた。
彼女は、自己紹介をはじめた。
彼女の声は、どこにもひっかからず、まっすぐ届いた。
誰も、夏の裏側のことを知らない顔で、聞いていた。
休み時間に、僕らは廊下の端で集まった。
「覚えてる?」
真帆が低く問う。
「覚えてる」
透がうなずく。
僕も、うなずいた。
灯子は、少し遅れて来て、僕らの輪に加わった。
彼女の手首には、もう痕もない。けれど、指先に冷たい風の感触が宿っている。
「戻れたね」
僕が言うと、灯子は小さく笑った。
「戻ったほう、に」
「ほう?」
「私たちが渡したもののぶんだけ、別の“私たち”が、代わりにここにいる。夏は、そうやって帳尻を合わせるんだって」
「じゃあ、あいつらは――」
真帆が、教室の中に目をやる。僕らに似た四人は、騒がしく笑い合っている。
「私たちの、別の夏。別の終わり。別の、選ばなかった方角」
「選べなかった、じゃなくて?」
透がつぶやき、僕は言葉に詰まった。
灯子は、窓の外の空を見た。
「どっちでも、いいのかも。ただ、対価は払った」
十二 消える順番
その日から、少しずつ、何かが減っていった。
僕は、自分の名前の「あ」の立ち上がりに、時々つまずくようになった。
真帆は、髪を結ばなくなった。風が吹くと、彼女はいつも髪を耳にかける。その仕草の回数が、日ごとに増えた。
透は、図鑑を開くと、ページの間から押し葉がふっと消えるようになった。
灯子は、ときどき教室のドアの枠を指で触れ、枠が嘘みたいに薄くなるのを確かめる癖がついた。
放課後、僕らは神社に行った。
茅の輪は片付けられていて、影の段はもう見えなかった。
裏の夏は、季節の衣装部屋にしまわれたらしい。
境内の石に腰を下ろしていると、町内会の古老がほうきを担いで通り過ぎた。
「おや。四人で何を」
「夏の終わりを見てるんです」
真帆が答えると、古老は目を細めた。
「いいことだ。終わりを見られる子は、始まりも見られる」
「逆さ祭りって、本当にあるんですか」
透がたずねる。
古老は、少し考えてから言った。
「あるさ。だが、見てはいけない。見れば、何かを拾ってしまうからな」
古老が去ったあと、灯子が僕らを見た。
「拾い直す?」
「何を?」
「置いていったもの」
言葉は、簡単に言える。
でも、戻すのはむずかしい。
橋はもう見えない。鍵穴も閉まった。
夏がしまわれてしまった今、僕らは“正しく”終わった側にいる。
そういうふうに、帳尻が合わされている。
十三 秋良の家の風鈴
九月のはじめ、風鈴の音が変わった。
母が言った。「今年は、少し低い音ね」
僕は、風鈴に口を近づけて囁いた。
――僕の名前を、呼んでみて。
風は、返事をしなかった。
代わりに、風鈴の内側で、小さな「あ」が一回、鳴って消えた。
それで十分だった。
僕は、自分の口の中の形を、指でなぞった。
喪失の輪郭は、毎日すこしずつ変わる。
慣れるということは、そういうことだ。
十四 灯子の秘密
ある夕方、灯子と二人で帰った。
空は高く、町は薄かった。
灯子は、電柱の影を踏みながら言った。
「引っ越して来た日の夜、私は、ここじゃないどこかで、自分の名前を三回、呼ばれたの」
「返事、したの?」
「一回目は、しそうになって、やめた。二回目は、しなかった。三回目は――わからない。
だから、私はここにいるのか、それとも“あっち”に置いてきたのか、自分でもわからない」
「怖くないの」
「怖いよ。だから、約束を作った。“拾い上げない”。自分に、何度も言い聞かせた。
……でも、たぶん、誰かが拾ってくれる日を、どこかで待ってる」
灯子は、笑った。
その笑いは、まっすぐで、夏の終わりの影に似ていた。
「だから、四人でよかった。三人でも五人でもなく、四人。橋は、四つの対価でできている。たぶん昔から、そう」
「昔?」
「去年、強く踏みすぎた誰かがいるって言ったでしょ。あれ、たぶん私」
僕は、返す言葉を持たなかった。
風が曲がり、電柱の影がひとつ、少しだけ濃くなった。
十五 忘れられる順番
やがて、町は僕らのことを少しずつ忘れた。
忘れ方には順番がある。
最初に忘れられるのは、僕らの小さな得意分野――真帆の早い走り、透の虫の名前当て、僕の自由研究の工作の手際。
次に、僕らの癖――鉛筆を噛む回数、窓の桟を指でなぞる癖。
最後に、名前の呼び方。
いつか、誰もが僕らの名前を少しずつ違えて呼ぶだろう。
それは、ひどく残酷で、そして不思議と、耐えられなくはない痛みだった。
四人で集まるとき、僕らは互いの名前を、丁寧に呼んだ。
秋良、真帆、透、灯子。
呼ぶたびに、橋の向こうで、何かが少しだけ揺れるのがわかった。
揺れているのは、たぶん、別の夏だ。
別の僕らが、たぶん、笑っている。
十六 新しい回覧板
ある日、回覧板が回ってきた。
そこには、また新しい紙が貼られていた。
『ご近所の皆様へ 夏休み中に転居のご挨拶――』
宛名は、僕らの知らない名字。
新しい子が、また来るのだ。
紙の角が、まだ硬い。
墨の匂いは、少しばかり心細い。
「……四人になる?」
真帆が言う。
「なるのかも」
透が答える。
灯子は、紙の字を指でなぞり、ふっと息を吐いた。
「約束を、教えてあげよう」
僕は、回覧板を抱えながら思った。
――僕らが“こちら側”で薄くなっていくぶん、“向こう側”は濃くなる。
夏は、いつも帳尻を合わせる。
そして、子どもは、毎年、少しずつ大人になる。
その代わりに、どこかで、誰かが、少しずつ消える。
十七 ダークエンド
九月の半ば、夕暮れが急に早くなった日。
僕は一人で神社に行った。
茅の輪は、もう倉にしまわれている。
境内の石段の影が、いつもより長い。
風は、骨だけになっていた。
鳥居の下で、誰かが僕の名前を呼んだ。
一度目は、いつもの呼び方。
二度目は、僕が選ばなかった方角を、そっと含んだ呼び方。
三度目は――
僕は、返事をしなかった。
でも、心の中で、ほんの少しだけ、頷いた。
たぶん、それは返事と同じ意味を持ってしまったのだろう。
足もとで、何かが静かにほどけた。
その夜、僕の家の風鈴は鳴らなかった。
母は気づかなかった。
僕は気づいた。
風鈴の中の小さな「あ」が、もう戻ってこないことに。
翌日、教室の席に座ると、前の席の子が振り返って言った。
「きみ、転校生?」
僕は笑って、うなずいた。
窓の外で、電柱が一本、まっすぐになった。
その瞬間、僕は理解した。
――帳尻は、たしかに合う。
けれど、その計算の終わりには、いつも、誰かの名前が余るのだ。
それでも、僕はノートを開いた。
一行目に、自分の名前を書こうとして、やめた。
代わりに、三つの名前を書いた。
真帆、透、灯子。
そして、行の端に、小さく、夏、と書いた。
ページをめくると、裏の余白に、風が通った。
見えない骨が、紙を鳴らす。
次のページが、ゆっくりと、勝手にめくれた。
――この町の夏は、耳鳴りみたいに続く。
耳鳴りは、たいてい、誰にも聞こえない。
だけど、僕らは知っている。
返事をしないこと。拾い上げないこと。
置いていくこと。
そして、いつか、誰かが拾ってしまうこと。
それが、僕らの冒険の終わりだ。
それが、次の誰かの冒険の始まりだ。
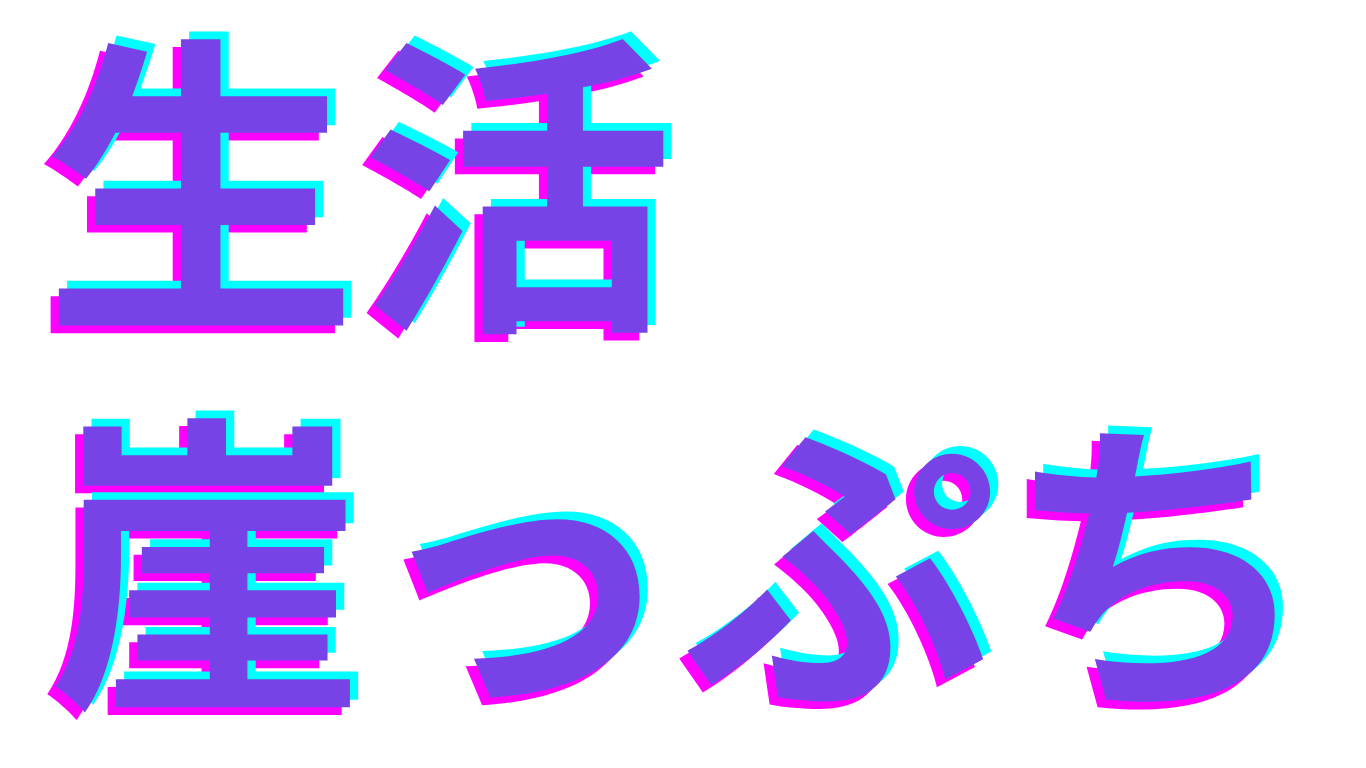


コメント